いつまでも富士山を世界遺産に
認定NPO法人富士山世界遺産国民会議 National Council on Fujisan World Heritage
みんなで考えよう
富士山インタビュー
その火山としての富士山を研究し、噴火した際の防災についての発信を続ける地質学者の吉本充宏さんに話を伺いました。
火山を研究する地質学者は火山のお医者さん的な存在のようです。
謎が多すぎるのが富士山の魅力です
−富士山を研究するようになったきっかけは?
2001年に東京大学地震研究所(以下地震研究所)に就職してからです。2000年に富士山で多発した低周波地震をきっかけに大型の研究プロジェクトがいくつも走り始めて、富士山の地質、構造を調べるプロジェクトに参加したのが最初でした。地震研究所に5年くらい在籍したあと、母校の北海道大学に戻りましたが、当時、私が助手をしていた藤井敏嗣先生がこちらの所長になった時に「もうちょっと富士山の研究をしようよ」と誘ってくださったので、2014年4月からこちらで再び富士山の研究を始めた、というわけです。
−いつ頃から火山に興味があったんですか。
実は獣医を目指して北海道大学に進学しましたが、ヨット部に熱を入れすぎて落第してしまい仕方なく地質学をやることになった、ということですね(苦笑)。最初は地質学でも古生物を専攻しようと考えていました。そちらの方が生物に近いし航海もありますからね。でもバイト料に惹かれて始めた火山の研究のための試料作りのアルバイトをする中で、授業とは全然違う火山の話を聞いたり、仲良くなった先輩たちの卒論や研究発表会に行くうちに、火山の研究もおもしろそうだな、と思い始めたわけです。
−そこからのめり込んでいったわけですか。
いや。修士課程に進んだのは、北海道駒ヶ岳をテーマに卒論を書き始めた年にバブルが弾けて就職難になったからです。その後、修士の途中で北海道駒ヶ岳が54年ぶりに噴火して、やめるにやめられず博士課程に進んだら、今度は周辺の火山も噴火して・・。いろんな噴火調査に加わっているうちに病みつきになった、というところです。
−まるで火山の方が先生に研究してもらいたがっているようですね。研究対象としての富士山の魅力を教えてください。
謎が多すぎるところです。多くの火山はだいたい数十万年活動します。箱根山は65万年くらいですしね。ところが富士山は活動を始めてまだ10万年しか経ってないのに3776メートルもある。10歳児で身長が2メートル10センチくらいあるようなものですよ。なぜそんなに急成長できたのかも、いくつかの学説はありますが、まだよくわかっていません。フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北アメリカプレートという3つのプレートがぶつかり、さらにその下に太平洋プレートが沈み込んでいるという複雑な環境の上に富士山があることが一つの要因だろうと考えられてはいますが、なぜそうなるのかはまだはっきりとはわかっていない。それを読み解きつつ、最近の噴火履歴を調べているところです。
−富士山を知ることが、防災にも役立ってくるとおっしゃっていますね。
そうです。例えば、よく風邪をひく子はひき始めからの症状の変化がわかっているから予防や対処ができますが、滅多に風邪をひかない子は実際にひくまでどうしていいかわからない。富士山は西暦800年から1000年くらいまでは割と頻繁に噴火していたのに、そのあとは1300年代と1500年代に一度ずつで、あとは1700年代の宝永の大噴火だけ。近代観測が始まってから全く噴火していないので、どういう癖があるか全くわかっていない。それで火山灰や溶岩を採取して過去の噴火について調べているわけですが、800年から1000年くらいまでは回数が多いけれど噴火の規模が小さくて、いつ、どういう噴火が起きたかという素性を理解するのは難しいですね。
−とはいえ少しずつわかってきていることはあるんですよね。
地震研究所にいた時に、富士山を総合的に研究する大型プロジェクトに参加して、藤井先生や何人かのグループで富士山の麓で何本かボーリングを掘ったら、富士山では見たことのない石が出てきた。それは安山岩で、小御岳の下にさらに別の火山があるのがわかり、それが先小御岳だったということがありました。いずれにしても富士山はまだまだわからないことばかりです。

富士山の火口は点在していて、その端から端までは約27キロメートル
−今、富士山の噴火の危険性はどれくらいあるのでしょう?
いずれ噴火するとは思いますが、今日現在、兆候は全くないですね。風邪のウイルスはいつ体に入るかわからないし、入ったら必ず風邪をひくとは限らないように、富士山もいつマグマが地下に入ってくるかわからないし、低周波地震がたくさん起きた2000年の時のように、何も起こらないまま終わることもある。先ほども言いましたが、富士山の噴火の癖はまだ解明できてないし、起きてきた変化が富士山にとって重大なのかそうでないのかわからない。今は、注意深く様子を見るしかない状態ですね。
−富士山の噴火に備えて知っておくべきことを教えてください。
富士山の火口は山頂以外にも点在していて、その端から端まで約27キロメートルある。今の段階では、どこで噴火するかは噴火するまでわからないということをまず、覚えておいて欲しいですね。そして、噴火したらとにかく遠くに逃げる。近くに住んでいる人は、ご家族と落ち合う場所を決めておくことです。助けに行くという行動は、逃げる流れと逆になる場合がほとんどで、1台が事故を起こしたら、多くの人が逃げられない状況を引き起こしてしまいますから。河口湖周辺に住んでいる人は、河口湖北岸の学校などにするといいでしょうね。溶岩は高温で1200度くらいあるけど速度はゆっくりで人が歩く程度、土石流は温度はそれほど高くないけれど車と同じくらいの速さで、火砕流は温度も高くて車より速い、ということも基本的な知識として持っているといいと思います。雪がある時期は溶岩や火山灰で雪が溶けて泥流の危険性があることも忘れないでいて欲しいですね。
−富士登山をする人たちが気をつけるべきことは?
富士山は火山である、と認識することがなにより大事ですね。御嶽山でも草津白根山でも、煙が上がった時にそれが噴火で、そこから石が飛んでくる、ということをわかってない人が多かった。だから本来であればすぐに逃げなければいけないのに、写真や動画を撮ってしまっていた。先ほども言ったように、富士山はどこから噴火するかわかりませんから、噴火する場所に応じて逃げるべき方向をしっかり確認しておく。山梨・静岡両県で発行している避難ルートマップがありますから、それを手に入れるといいと思います。あとは、紙の地図ですね。電子媒体は電池が切れたらおしまいですから。山小屋の方には、避難する場合はたとえ遠回りでも山頂と噴火した場所を結んだ線とその延長線上はまたがないように、とお願いしています。火口列は延びていく可能性がありますからね。装備は、基本的な登山の装備で大丈夫です。紙の地図も、水や食料の他に腐らないドライフードを持っていくというのも、登山の基本ですから。
−展示室(富士山サイエンスラボ)で富士山の模型を使ってどう溶岩が流れるかを見せていただきましたが、あれはとてもわかりやすいですね。
あれは赤色立体図という非常に精巧な富士山の模型で、そこに少し粘り気と色をつけた液体を流すことで溶岩がどう流れるかが実感できる。直感でイメージしているのとは違う流れ方をすることがあるのもよくわかります。地元の小学生たちが来ると、いろんなところから液体を流して見せています。そうすればいざという時、どこにどう逃げるべきか判断できますからね。興味がある人は、ぜひ、来た時にスタッフに声をかけてください。
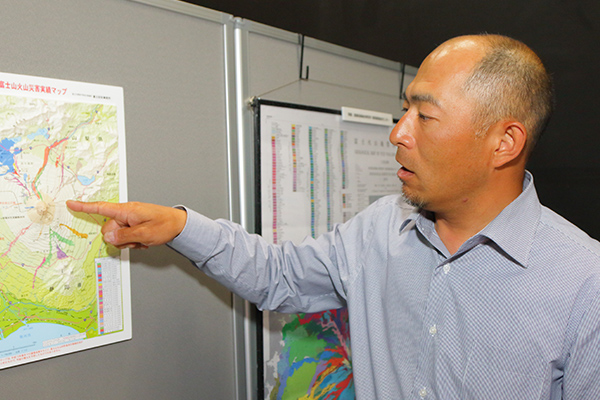
たまに乗せてもらうヘリコプターから見る富士山は本当にきれいですよ
−関西のご出身ですが、初めて実物の富士山を見たのはいつですか。
小学校の修学旅行で富士山に来た時です。その時は青木ヶ原の周辺だけでした。当時、富士山の周辺ではいろんな不思議な現象があるぞ、と聞かされていたのでビビっていた記憶しかないし(笑)、青木ヶ原の鬱蒼としたイメージしか残っていません。まさかここに住んで、研究するとは思っていませんでした。
−その後、富士山に来たのは?
2001年に地震研究所に就職した直後に参加した最初のプロジェクトで来ました。富士山の構造を調べるボーリング調査の候補地選定のために、河口湖周辺から五合目辺りをウロウロしていました。山頂にも十数回は行っていると思います。ただ山頂も私にとっては調査の対象の一部でしかないので、調査がなければ行くことはないですね。
−調査以外では山には登らないということですか。
ええ、私が登っているのは火山だけです。
−火山の研究のおもしろさはどんなところにありますか。
不謹慎かもしれないけれど、見て楽しいですね。噴火は天然の花火のようなものですから、夜はとくにそう感じます。あと、我々が日頃見ている地層というのは起こったあとのものでしかなくて、それがどうやって、どのくらいの時間をかけてそこに溜まったかはよくわからない。でも今、起きている噴火やそれによって溜まってきたものを見ることで、地層のこともある程度わかってくる。それがおもしろいですね。
−一番きれいだと思うのはどこから見る富士山ですか。
たまにヘリコプターに乗せてもらう機会がありますが、上から見ると本当にきれいですよ。五合目から上が雪で真っ白になっていたり、雲の中から飛び出している姿もすごいなあと思います。火山の研究を始めてから写真を撮るようになりましたが、上から見る富士山は、撮っていても楽しいです。とはいえ、火山ですからね。噴火したらその影響は非常に大きいので、防災のための研究をさらに進めないといけないし、それを防災に役立ててもらえるように、火山のこと、富士山のことをもっと知ってもらう活動も積極的にしているところです。


よしもとみつひろ
1970年 兵庫県宝塚市出身 西宮今津高校卒業後、北海道大学理学部に進学。北海道大学理学部地質学鉱物学科卒業、同大学院理学研究科地球惑星科学専攻博士課程修了。東京大学地震研究所助手、北海道大学大学院理学研究院助教を経て現職。大学時代はヨット部に在籍し、全国大会にも出場した。趣味はアウトドア全般。最近は、野球をやっている小学校6年生の息子さんと毎週末野球をしている。日本火山学会理事(防災担当)。山小屋をどう強化するかなども研究中。